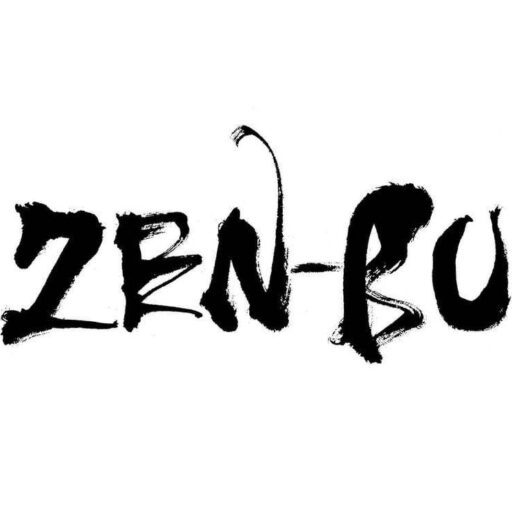2.省資源・省エネルギー・低コストで、 広域の土を豊かにする「土づくり」技術の確立
未来の食料供給を安定させるためには、年々と土を豊かにしていく農業技術の確立が必須になってきます。良い土壌に育つ作物は、異常気象(高温障害や水不足、日射量不足)の影響を受けづらく、品質と収量も安定するからです。一方で、同じ土地において種を更新していく農法も積極的に取り入れていくことで、より地域に適した種子を作っていくことも目指します。
まず、私たちの実証研究では、輸入資源である農薬や化学肥料は「地域自給」や「国内自給」といった観点から、あるいは土の劣化を招くという要因から使用しません。栽培品目としては、野菜よりも米や大豆、油脂植物などの穀類や、芋類などに重点をおいていきます。これらの穀類は、現状の農業界の元では超大規模農家でないと採算が合わない経済構造がありますが、有事の際には最も食料自給に貢献してくれるものであり、私たちの食事の土台をつくる品目だからです。
また、新しい機械を作り出すことでできる限り少人数で広い面積をカバーできる農法を開拓しつつも、同時にアナログな道具を大人数で使っていくことで、一人の一日当たりの作業時間を減らす農法・運営体制も模索していきます。
以上を踏まえた上で、本研究では、農業初心者でも取り組むことができ、これまで以上に地域資源や自然界にあるエネルギーを最大限に活用した土づくりの方法論を実証実験していきます。また、取り組みを進める中で五感を通じて自然の摂理や循環への理解を深めていくことができる学びの道筋も模索していきます。以上のポイントをクリアしうる農法の中でも、国内での実証研究や普及がほぼ進んでいない以下の三つのアプローチを中心に実証実験を行います。
- 不耕起・部分耕起栽培 (省力化、土中環境保全、水不足対策、etc.)
- カバークロップ・緑肥 (土壌の富栄養化、省力化、高温障害・水不足対策、etc.)
- 地域循環型の堆肥製造と活用 (地域の未利用資源の利活用、短期間での土壌の富栄養化)
特に1)と2)は、農作業行程そのものを省略するだけでなく、植物に土中の栄養分を作って蓄えてもらうことを目的とする農法でもあります。このため、土に投入する肥料の使用量や、耕運や散布に使われる重機のエネルギー使用量を大幅に減らしつつも、土をよくすることができるポテンシャルを秘めています。
見出し
Toggleⅰ) ライ麦カバーによる大豆の無農薬・不耕起栽培
コンセプト
日本における無農薬・大豆栽培の最大のネックとなるのが、除草作業です。通常だと、ひと夏に5回ほど広大な大豆圃場の畝間を丁寧に除草しなくてはなりません。一回の除草には人手も時間もかなりかかるので、ここの手間を半減以下にすることができれば、栽培面積も2倍以上に増やしていくことが可能になります。また、広大な畑作面積で土づくりを行うのにも、通常ですと大量の堆肥の製造・散布コストがかかります。
こうした手間を大幅に減らしていくために「ライ麦(秋〜初夏)→大豆(初夏~秋)」の順で大豆を主作物とする省力・省資源・不耕起栽培を実験しました。
取り組み
【実験内容】
ライ麦を秋に植え、翌年の春に倒して、そのライ麦カバーの上から大豆を植えるという不耕起栽培。びっしりとおおい茂ったライ麦が地表を覆い、根っこから発芽抑制因子を分泌するため、種子が小さい雑草の発芽と成長を抑え、夏場の高温障害や水不足の影響も受けにくい圃場をつくり出してくれます。また、大豆を植える前の耕運作業や畝立て作業もカットするため、大幅な作付けから除草の手間が省かれることが期待されました。
ネックとなるのは、太く大きく育ったライ麦を倒した後に、どのように大豆の播種をしていくかです。きちんと地中に種を入れることができないと発芽しないし、雨がしばらく降らないタイミングで播種をしてしまうと、播いた大豆も発芽してくれません。今回は、厚みのあるライ麦の上からきちんと大豆を地中に入れていくことができる播種機や播種の方法を4通りほど試してみました。
【評価】
- 収量:播種と発芽が安定せず、圃場によってまちまちだが、大豆はスクスクと育ち、実もずっしりと実った。
- 抑草:多くの雑草に対してはかなり効果がある。しかし、根が地中に残って増殖する多年草(ギシギシなど)に対してはライ麦カバーは上手く機能しないため、完全な雑草抑制には至らなかった。
- 土への影響:良さそう。
- 作業の手間:従来の1/4ほどに。
- 実現へのハードル:あと2~3年でかなり確立できそう。播種の方法・機械がどれだけできるかと、栽培のローテーションがどのように確立できるかによって実現可能。
- 将来性:とてもあるので、実験は継続。
耕さない畑に大豆を播種していくためには、土を柔らかい状態に保つ必要があることがわかりました。ライ麦を倒すために重機であるトラクターやローラークリンパーを使うと、タイヤ圧によって土が踏み固まってしまい、不耕起栽培の播種機を使ってもなかなか大豆が地面に植っていかないことが分かりました。
今回発芽率が最も高かった圃場は、人力でライ麦を踏み倒した後に「プランタデイラ」というブラジルで昔ひろく使われていた人力播種機で直接一つひとつ地面に大豆を植えていったところでした。
ⅱ) ヘアリーベッチ緑肥を活用した水稲の不耕起栽培
コンセプト
水田稲作において多収の鍵を握るのは、土中で使われる窒素分と言われており、現在の有機農法ではこの窒素分を外部から肥料として投入していくやり方が一般的です。しかし、日本で使われている肥料のうち約99%は輸入によって賄っています。また、有機肥料分は重量的には重く、資源的にも限りがあり、コスト的にもどんどん高くなっています。そんな中、生態活動の一環として空気中の窒素を地中に溜めていく働きをする主にマメ科の緑肥・ヘアリーベッチが注目されています。
また、かつて千葉県を中心に実践農家さんが一定数いたと言われる水稲の不耕起栽培ですが、30年ほど前に専用の田植え機が販売中止になってから、この農法を実践する農家さんがほぼいなくなってしまいました。しかし、この農法を採用できれば、稲作の栽培コストが大幅にカットされます。秋の耕運、春の耕運、施肥、代かきといった四つの栽培工程をまるッと省くことができるからです。もしこの農法に結果が伴う場合、同じ人数と労力のもと、栽培面積の拡大が可能になります。
こうした期待のもと、神戸大学の庄司教授から試作された不耕起田植え用の自作田植え機もお借りして、地域でもとても珍しい田んぼの不耕起栽培にチャレンジしました。
取り組み
【実験内容】
ヘアリーベッチを緑肥作物として秋に作付けして、田植え前の施肥や耕運、代かきを全て省いて不耕起栽培を行いました。ヘアリーベッチは、窒素を空気中から土中と地上の植物体内に固定する働きがあるため、枯れたヘアリーベッチそのものが稲の栄養源になっていきます。ヘアリーベッチも雑草種子の発芽を抑える化学物質を根っこから分泌するため、雑草の抑制には一定の効果がありました。
結果:田んぼの水はけが良くなりすぎたことで、常時田んぼに水を入れなくてはならず、それによってこの農法が成立する田んぼが多く存在しないことが判明しました。また、入水の水がとても冷たかったため、全体的に稲の生育が遅くなってしまい、ヘアリーベッチで抑草効果があった期間でさえ稲が育たず、結果的に稲が小さく育ってしまい、収量にも影響してしまいました。
【評価】
- 収量:反収2.5俵なので、全然良くない。
- 抑草:ヘアリーベッチ自体は田植えから1ヶ月くらいは雑草の抑草に効果があった。でも、代かきを行っていないために田んぼの水はけが良くなりすぎてしまい、常時田んぼに入水し続けなくてはならず、その水温が冷たすぎて稲の生育も大幅に遅れてしまい、結果的に雑草とのレースに勝てなかった。
- 土への影響:水温の問題があったため、土質への影響は不明。
- 作業の手間:作付け前の作業は従来の1/2ほどに。でも、水管理は逆に増えた。
- 実現へのハードル:水の確保ができる田んぼでないと難しい。また、代かきをしないために田んぼを平らにすることが難しい。水はけが悪いところだと実現可能性は高まるが、緑肥はヘアリーベッチではなくて蓮華になる。しかし、蓮華には発芽抑制因子を分泌する力がないため、除草はこれまで通り必要になる。また、不耕起栽培用の田植え機を自分で製作する必要がある。
- 将来性:正直あまりなさそうなので、来年はやりません
ⅲ) 地域資源を活用した高性能腐植堆肥の製造
コンセプト
自然農法無の会では2012年の堆肥場建設以降、地域内で廃棄されるはずだった有機資源を十分に発酵させ、土に還しつづけてきました。この堆肥づくりこそが自然農法無の会の農作物の美味しさの秘密であり、安定した収量をあげる生命線でもあります。
一方で、堆肥製造には様々な課題もあります。第一に材料が農家・食品加工業者・廃棄物処理業者に依存しており、安定した品質・製造量を担保するのが困難であること。第二に製造にあたっては切り返し作業や散水作業にかかる燃料消費や設備コストが甚大であること。第三に地域内の様々な事業者間で有機資源を循環する取り組みであるにもかかわらず、堆肥製造にかかるコストをすべて農家が負担していること。
また、家畜排泄物による水質汚染や土壌汚染が世界的な課題となっていますが、自然農法無の会で製造する堆肥材料はすべて植物由来の有機資源であり、この課題解決に対しては貢献できていない現状も打開したいと考えてきました。
これら課題の解消に向けた第一歩として、専門家指導のもと高性能腐植堆肥の製造に向けた取り組みを始めました。
取り組み
【活動内容】
奥会津のウッドチップや会津地域の茅葺き屋根の茅を活用して、現在自然農法無の会で製造している腐植堆肥の品質向上を図ります。過去25年間、国内外600ヶ所以上で地域資源で堆肥づくりの指導をされてきた専門家の方に技術指導をお願いしました。
堆肥製造のために、2月の釧路の大型牧場における高性能堆肥場の視察に始まり、3〜7月の地元資材の選定、そして8~9月に会津における実証実験を行いました。堆肥の切り返し方や水分調整、切り返しのタイミング、温度測定など、かなり具体的な指導をしていただきました。
【評価】
- 堆肥の完成度:まだ不明。発芽実験は芳しくない結果に。晩夏に製造して春作物である玉ねぎとニンニクの圃場に播いたため、春以降に検証を行う。
- 土への影響:堆肥が完成して施肥をした状態なので、来期に判明。
- 作業の手間:従来よりもかなり工数が増える。
- 実現へのハードル:頑張って材料を適量集めていくことと、堆肥製造の設備(主に堆肥攪拌機や、材料の”ふるい”を行う設備など)を揃えていく必要がある。また、廃棄物処理業者としてのライセンスを取得すれば、別の収入源が確保できる可能性あり。
- 将来性:まだまだ実験の余地あり。
ⅳ) 年2回の精密土壌検査による土壌状態の把握
取り組み
土壌の健康を正確に把握するために、この道で最も精密で多角的な検査をしている技術コンサル・株式会社Agsoilの南さんにお願いをして、年2回の精密な土壌検査を実施しました。この検査を通して、土壌の化学性や物理性、栄養素のバランスを詳細に調べ、過剰な肥料の使用を避け、必要な栄養素のみを適切に補充する農法の論拠を学びました。
この結果、無の会のほとんどの圃場には既に十分な栄養素が含まれていることが分かり、無肥料に近い栽培が可能であることが判明しました。
ⅴ) 農園視察
取り組み
ベテラン農家さんや団体さんの有機・循環型農法を学び、自分たちの農法や営農形態を客観視するために、全国各地の先進的な取り組みを視察しました。
視察農園名をクリックすると、先方のHPへ飛べるものもあります。
【2024年1月~2025年1月における視察農園一覧】
- 北海道・釧路市、仁成ファーム:大規模な高性能腐植堆肥の製造現場視察
- 北海道・長沼市、メノビレッジ長沼:羊の放牧・ミックスカバークロップ・在来小麦の不耕起栽培の現場視察
- 北海道・置戸町、Maoi Cover Seed主催のリジェネラティブ農業の実践研究会である「大地再生の旅」における、米国Understanding Agから派遣された農業指導員・Chuck Sumbreさんの同時通訳 (北海道新聞の記事挿入)
- 岩手県・岩泉市、なかほら牧場:中規模・山地放牧酪農の現場視察、取材
- 岩手県・花巻市、ウレシパモシリ:養豚・パーマカルチャー視察
- 兵庫県・宍粟市、リアプラスの若手農家と、栽培方法、経営について情報交換
- 福島県・会津坂下町、やますけ農園における最高品質鶏卵による養鶏場と業務提携
- 福島県・二本松市、にったOrganic Farmにて、有機野菜の多品目栽培の経営ヒアリング
- 山形県・川西町、浦田農園で、大豆の有機栽培を中規模に行う現場を視察
- 千葉県・匝瑳市、Patagonia提携ファーム・Three Little Birds合同会社にて、大豆の部分耕起栽培とソーラーシェアリングの現場視察
- 米国・バーモント州、Boundbrook Farmにおける有機水稲・合鴨農法の現場支援
- 沖縄県・本部町、長堂ファームにおける中規模の有機マンゴー栽培の視察
- 静岡県・静岡市、村上園におけるBMW農法による有機緑茶栽培の視察
- 佐賀県・鳥栖市、(株)三生における、イノシシの狩猟研修
- 栃木県・那須塩原市、学校法人アジア学院における地域自給型有機農業を軸とした人材育成プログラムの設計と運営状況の視察
- 宮崎県・えびの市、本坊農園と水田除草の情報交換
- 宮崎県・えびの市、鬼目養鶏場で、鶏糞堆肥を農業や牛飼い、エネルギー自給のために循環させるモデルを視察
- 福島県・喜多方市の大竹久雄さんに、機械、微生物を用いた水田除草の方法の指導を受ける
- 福島県・会津美里町の斎藤富雄さんに、稲作の施肥と水管理の考え方、野菜栽培の技術を習う
- 大分県・日田市、ときこえ村で人集め、コミュニティづくりに資する考えを教わる
ⅵ) 特殊な栽培
取り組み
真面目な栽培ばかりでは遊びがないため、余興的に非科学的・非効率的な人力栽培も行いました。
隕石の微粉末を固めたセラミックボールを大量に使い、手植え・人力除草で育てた水稲や、しめ縄用に真菰を栽培することにしました。真菰に関しては、除草の手間を省くために、普通は機械でしか使うことのない紙マルチを人力によって敷き詰めながら植えていく、非常に過酷な紙マルチ田植えを敢行。気持ちの良い汗を流しました。
ⅶ) 学び・総括
今年度は、上記のような検証項目そのものを洗い出す一年でありました。他の仕事やこれまでの無の会の栽培業務に追われてしまい、新しい農法の大枠に沿って実践することに精一杯で、栽培時に検討すべき項目の選定やデータ収集などは、手が回りきらなかった部分も多くあります。しかし、今年大まかな栽培実践を行ったことにより見えてきた、来年度から注意すべきポイントが以下の通りになります。
- 作期作型の設計:いつ、どのように作付けをして、どんな作業をして、収穫まで持っていくのか
- 抑草のポイント:作付け方法や除草方法をどのように最適化するか
- カバークロップの選定と配合:どの種類をどの分量で混ぜた上で植えていくのか
- 輪作サイクルの設計:i.e. 菜種(秋~春)→大豆(春~秋)→麦(秋~初夏)→蕎麦(晩夏~秋)→大豆など
- 栽培コストと労力に対する収量:安くなるのか、楽になるのか、収量は落ちないのか
- やればやるほど土が豊かになっているか:土壌分析、収量データ等を通して
特に来年度以降は、より本格的に「良い土」の定義を追求していきたいと思います。そして、検査の方法そのものも低コストで、誰でもできるものを確立していきたいと思っています。
具体的には、土中の生物活動の指標として土中二酸化炭素量を測定したり、Slake test(スレイクテスト)を行うことで土壌団粒構造の形成度合いを調査したり、スコップで垂直に穴を掘ることで土壌団粒構造を確認する方法を取り入れます。これらの測定方法は海外のリジェネラティブ農業の農業者や技術者の間で活用されている方法ですが、日本の農家さんの間ではあまり普及していません。また、これらは全て低コストで実施できるものでありつつ、土壌の健康状態を診断できるものであり、土壌改良の効果をより精緻に評価していきます。
また、来年は全国の自然農家との連携も強化していきます。他の農家さんと情報交換をしていきたいと考えている農家さんは多く存在することが分かっており、この横の関係性の構築ができることが業界全体のレベルアップにつながっていくと感じました。
異なる地域での実践事例や成功例を共有し、相互に学び合える地域自給を目指す農家ネットワークを構築することで、各地において持続可能な農業技術を向上したり、情報交換をしていく関係性を築いていきます。