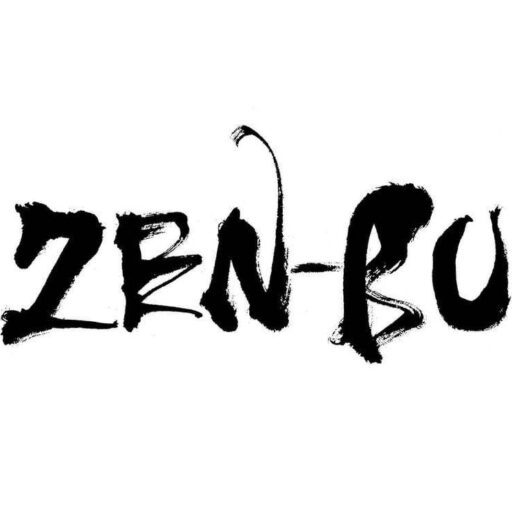1.「百姓一揆コミュニティ」の形成
未来の食料供給を安定させるためには、年々と土を豊かにしていく農業技術の確立が必須になってきます。良い土壌に育つ作物は、異常気象(高温障害や水不足、日射量不足)の影響を受けづらく、品質と収量も安定するからです。一方で、同じ土地において種を更新していく農法も積極的に取り入れていくことで、より地域に適した種子を作っていくことも目指します。
まず、私たちの実証研究では、輸入資源である農薬や化学肥料は「地域自給」や「国内自給」といった観点から、あるいは土の劣化を招くという要因から使用しません。栽培品目としては、野菜よりも米や大豆、油脂植物などの穀類や、芋類などに重点をおいていきます。これらの穀類は、現状の農業界の元では超大規模農家でないと採算が合わない経済構造がありますが、有事の際には最も食料自給に貢献してくれるものであり、私たちの食事の土台をつくる品目だからです。
また、新しい機械を作り出すことでできる限り少人数で広い面積をカバーできる農法を開拓しつつも、同時にアナログな道具を大人数で使っていくことで、一人の一日当たりの作業時間を減らす農法・運営体制も模索していきます。
以上を踏まえた上で、本研究では、農業初心者でも取り組むことができ、これまで以上に地域資源や自然界にあるエネルギーを最大限に活用した土づくりの方法論を実証実験していきます。また、取り組みを進める中で五感を通じて自然の摂理や循環への理解を深めていくことができる学びの道筋も模索していきます。以上のポイントをクリアしうる農法の中でも、国内での実証研究や普及がほぼ進んでいない以下の三つのアプローチを中心に実証実験を行います。
- 不耕起・部分耕起栽培 (省力化、土中環境保全、水不足対策、etc.)
- カバークロップ・緑肥 (土壌の富栄養化、省力化、高温障害・水不足対策、etc.)
- 地域循環型の堆肥製造と活用 (地域の未利用資源の利活用、短期間での土壌の富栄養化)
特に1)と2)は、農作業行程そのものを省略するだけでなく、植物に土中の栄養分を作って蓄えてもらうことを目的とする農法でもあります。このため、土に投入する肥料の使用量や、耕運や散布に使われる重機のエネルギー使用量を大幅に減らしつつも、土をよくすることができるポテンシャルを秘めています。
見出し
Toggleⅰ) 0次化プランの設計とパートナー契約の締結
コンセプト
「0次化プラン」は、従来の「薄利多売型の作物の生産販売(=第一次産業)」という農業のカタチから脱却して、「年々と土を豊かにしていく(=第0次産業)」という行為にお金が支払われるという新しい経済の流れを社会に創っていくことをゴールとして設計されました。これが実現すれば、地域資源を基本として、環境負荷も大きく低減される持続可能な農業が可能になるからです。
農業を第0次産業化していくための具体的な施策として、福島県会津美里町を拠点に、日本の雪国気候における地域循環型の自然活性化農業モデルを構築していきます。大きく以下の三つを実現していきます。
- 自然農法(=土を年々と豊かにしていく農法)の確立
- 地域資源による生産システムを持った中規模農場の増設
- それらを支える農業人才の集約と育成
こうした農業が各地に起ち上がっていく流れをつくるために、必要な初期投資と運営経費を全て農家自身が単体で背負うのではなく、30~50人のパートナーさんが一緒に分割して支え合っていくコミュニティ・サポート型の経済モデルをご提案させていただきました。
取り組み
2023年11月から2024年12月まで、マンツーマンでは200人ほど、講演会も含めると400人以上にこのプロジェクトの計画と0次化プランについてお話しをさせていただきまして、現在36組の0次化パートナーさんが誕生しました。
【2024年に実施したプロジェクト講演会の一覧】
- 2/14 会津若松、会津商工中金
- 2/17 東京・新宿、アトリア参宮橋 (“本来の自分の在り方・生き方”を探求するコミュニティAtlyaの活動拠点)
- 3/14 新庄最上・有機生産組合 (日本の大豆自給率を約4%を上げた「大豆トラスト運動」の火付け役となった生産団体)
- 3/21 会津若松、会津商工中金
- 4/7 東京・有楽町、Allbirds (サステイナブルなグローバルなシューズブランド)
- 5/18 いわき市・市民団体(SSC株式会社主催)
- 6/21 東京・神宮外苑前、春巻きクラブ (マッキンゼーのインターンのメンバーの集まりを母体として1996年に設立された、お互いから学びあう機会を提供する会)
- 7/9 会津美里町、まちづくりBプラス(会津美里町のNPOが中心になって立ち上げたまちづくり、人材育成をすすめる任意団体)
- 7/23 東京・恵比寿、長谷園 (三重県・伊勢市で190年以上続く伊賀焼の窯元・長谷園が、東京・恵比寿に構えるアンテナショップ)
- 8/2 オンライン、GPSSサステな会 (再エネ事業のGPSSグループの社員さんが「サステナブルな社会の実現」に向けて、毎週サステナビリティに関連する様々なテーマについて学び、話し合う場)
- 8/16・8/18 オンライン事業説明会
- 9/5 東京・新宿、アトリア参宮橋
- 9/12 会津若松、会津経済倶楽部
- 11/23 会津若松、高畠熱中小学校(山形県高畠町から全国に広まった、大人の学びと交流、挑戦の場を提供するコミュニティ)
- 12/18 オンライン、立教大学ビジネススクール
引き続きパートナーさんの輪を拡げつつも、パートナーさん同士の横のつながりづくりにも励んでいこうと思います。
ⅱ) コミュニティ拠点の建設
コンセプト
本格的な「土づくりコミュニティ」を作っていくためには、会津に多様なメンバーが集い、寝食を共にしながらプロジェクトを推進していくコミュニティ拠点が必要になります。しかし、はるばる日本の僻地・会津に全国・全世界から人才が集い、共に事業を形にする流れをつくるためには、その場が一般的な民家では不十分だと感じました。滞在するだけで全身がおのずと活性化して、意識が変わり、土地や百姓の歴史、伝統文化や技術、素晴らしい自然への理解が深まっていく— そんな唯一無二の空間を作ることができないかと考えました。そんな中、偶然にも地域に眠っていた歴史的な古民家が手に入りました。その流れの中で、この場所を古民家の本質に則って現代風に再生していくことになりました。

取り組み
私たちは、明治元年に結ばれた「会津百姓一揆」の際に、会津盆地で唯一破壊されずに残った元庄屋・旧馬場邸を再生しました。武田信玄の右腕と呼ばれた馬場美濃守の直系一族の末裔が会津に落ち延びてきたあと、家臣と共に江戸時代中期に建てた、茅葺き屋根の大きな古民家です。会津美里町・箕作部落(集落)の発祥の家であるために、部落での地番も「一番地」となっています。数十年前に行われた当時の家主・馬場さんによる現代的な内装工事の前には、県の重要文化財に登録される予定だった歴史的な建物です。
敷地内に古い蔵が三つついており、母屋は約87坪の大きさがあります。蔵の中には、会津百姓一揆の際に他の庄屋では燃やされてしまった文書や手形(江戸時代に徴税で使われる税率や農作物の収量にまつわる記録など)が全て残されており、これらの書物は全て福島県立博物館に寄贈されています。
2022年の10月ごろ、横浜にお住まいの持ち主の方がこの家の解体を決め、無の会の茅堆肥の原料となる目前の状態をたまたま発見し、歴史的価値を引き継ぐためにも土地や農地と共に購入に至りました。
2023年10月に地元・会津の工務店・(株)志木の棟梁さんと打ち合わせをしたところ、建物の老朽化による歪みが激しいことが確認されました。(株)志木は会津の伝統工法で、住んでいる人がどんどん健康になっていく自然素材の家を建てる工務店です。話し合いの結果、家そのものが重要文化財であるこの家を一度解体し、古材を使った新築として再生し、その施工を(株)志木に依頼することが決まりました。
この事業に対する信用と話題性が生まれ、この拠点に全国・全世界から志のある人々がどんどん集まり、新しい仲間となっていく流れを作ることができます。建材には国産の自然乾燥の木材と自然素材を使い、会津の大工・職人さんが丁寧に施工することで、これから200年以上使い続けられる家を建設しました。ここに訪れる人々が健康になり、環境意識がさらに高まる「場」が生まれます。
今回集めさせていただいた初年度の契約金のほとんどは、この第一コミュニティ拠点を整備していくための資本金として使われました。
ⅲ) 自然環境・社会の土づくり
コンセプト
第0次産業としての「土づくり」は、単に「農地の土」だけを豊かにするのでなく、地域の「自然環境」や「地域社会」も同時に活性化させていくことを意図しています。そもそも、農業という産業は地域の広い自然環境の中での循環や、地域の文化、そして地元について学んだ大人や子どもたち、地域経済の中で成り立っています。こうした農業という産業が盛えていくための自然環境や社会の「土」となる部分に対して、私たちは積極的な「土づくり」をしていきます。
こうした活動は農業の振興のみならず、自然環境や社会全体の活性化に繋がっていくものだと認識しています。現在はお金になりづらいが、長期的には自然界や社会にとって大切な取り組みをまるまる請け負っていくことで、新しい未来が作られていくと直観しています。
取り組み
私たちは会津を拠点に活動をしているため、会津を中心に以下のような活動に取り組んで来ました。
【自然環境の整備】
- Punakohaによる農地の環境改善ワークショップ:農地における水はけと風通しの改善を目的とした施工
- 杉屋・箕作・西勝・松沢、永井野地区における農業環境整備 (通称:人足)
【共育・文化事業】
- 会津美里町立宮川小学校・総合学習「花おくらとサイカチの実を使った伝統紙漉き」授業の設計に携わる
- 「虫送り」「西勝彼岸獅子」の継承活動
- 地域の夏祭りで鼓笛を担う
- 大阪大学「GEDOKU」講座開設準備(2025年秋開講予定)
- 東京大学農学部にて、1コマ講義
- 会津でしめ縄制作・指導を行う「ゆいまーる」と提携して真菰の栽培
- 「てわっさクラブ」で地域のお年寄りから籠編みを習う
【地域事業との提携・支援】
- 都立立川高校「良い消費者になる」総合学習プログラム(2泊3日)
- 三菱商事・農泊型企業研修プログラム(2泊3日)
- 「高田納豆」でお馴染みの会津に二軒しか残っていない地元の納豆屋さん・新田商店にて、人手不足に困っているタイミングで納豆製造のサポート
- リモートメンバー・本田ご夫妻のセレクトショップ「&FARMS」の会津若松への店舗移転準備・店舗PRイベントに出店
- 会津若松のLotus保育園の給食
- 会津若松の金堀重機の感謝祭に出店
- 会津坂下町の自然養鶏・やますけ農園との資源循環提携
- 多品種の鶏飼育を行う大久保さんの農業設備の修繕技術伝授を受けつつ、諸々のお手伝い